真っ白なホワイトボード VOL.11
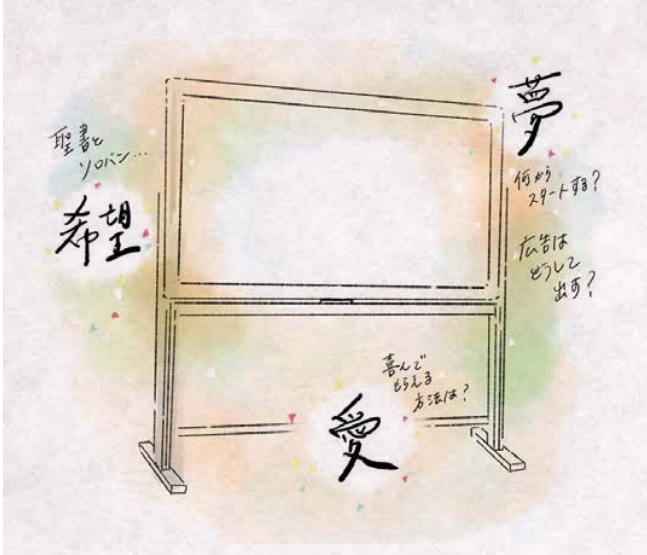
~福祉をサービス業へ、世界への挑戦物語~
第3章「裏切りから、成長へ」
その3「日本一小さな老人ホーム誕生」
「サービス業としての福祉の型を極めたい」という佐藤の情熱。「採算を度外視した事業は悪であるという木村の思い。羅針盤を失った航海の途上で道を模索していた二人の元へ一本の電話がかかってきた。
建設中のマンションを老人ホームにしないかと提案されたのだ。老人ホームの建設なんて尚早すぎると思いながらも、訪問介護の限界を痛感していたこともあって、二人は勉強がてら見学に訪れることにした。
≪老人ホームは街の喧騒が聞こえる所がいい≫
かねてからそう感じていた佐藤はひと目見て天の配剤だと思った。傍らの木村を見ると木村も佐藤を見返している。木村は大きく佐藤に頷き返した。
高齢になっても人生は続いてゆく。先進の医療、家族をはじめとした豊かな人間関係、気が向けば買い物をし、映画を見たり、美味しい珈琲店にも入りたい。それまでの老人ホームは郊外型がほとんどだった。いくら自然環境に恵まれていても、豪華な設備が整っていても、人里離れた施設ではそれが叶わない。都市型の老人ホームなら、何一つ諦めることなく人生の続きを送れるのだ。
だが悲しいかな、スタートしたばかりの小さな会社には資金も信用もなかった。
夢のまた夢か。諦めかけた時、地元の地方銀行の支店長である鈴木から連絡があった。
「佐藤さん、木村さん、もう一度話を聞かせてくれませんか。」
桜の花がほころびかけた春まだ浅い日、二人は地元の銀行を訪れた。数日前、佐藤は飛び込みで入ったその銀行に、赴任したばかりの若い支店長をみつけて直談判していたのである。
当時はバブルの真っ最中。鈴木支店長のもとにくるのは、この土地を買ったら儲かるからという、そんな話ばかり。その中でこういう事業をしています。社会福祉をサービス業として株式会社としてやっていると話す佐藤に鮮明な印象を受けながらも、融資には慎重にならざるを得なかった。
しかし何度も話すうちに、良いサービスをしてそれに対して報酬をいただくのだという佐藤と木村の事業の理念に心を動かされ始めていた。他の銀行の人は話も聞いてくれなかったというが、二人にはビジョンと理念を持った経営者としての迫力があった。理屈が通っていた。そして、何より、鈴木の銀行マンとしての計算に裏打ちされた勘が、この事業は間違いなく成功すると告げていた。
≪20年後30年後、老人の人口は増えていく。そこそこお金のある人は良いサービスを受けたくなるだろう。算数に落とし込んだら?よし、大丈夫だ。≫鈴木は融資を決めた。
全17室という日本一小さな老人ホーム「ロングライフ長居公園」はこうして誕生するのである。
つづく