真っ白なホワイトボード VOL.7
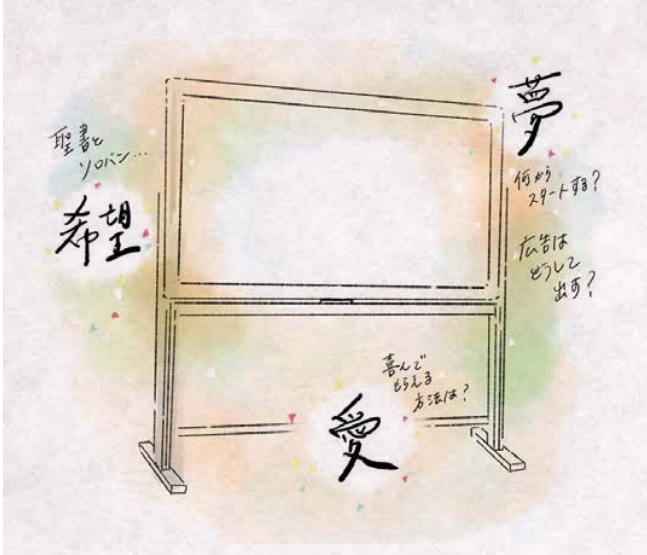
~福祉をサービス業へ、世界への挑戦物語~
第2章「介護はサービス業」
その2「自らの役割」
高齢者を自宅で世話することが、当たり前とされてきたこの国。そしてその介護の仕事の多くを女性、特に嫁いできた嫁が担ってきた。この社会的な問題は一目置いておくとして、家族が行う高齢者や障碍者の日常生活での介護のことについて考えてみたい。
ベッドから起こしたり、着替えなどはコツを掴めればなんとかできる。車いすなど条件が整えば、外に連れ出したり、電車や車で移動も可能だ。食事や排泄の世話も、手間はかかるがやれないことはない。しかし、どうしても家族だけではやりきれないのが入浴介助である。
一般的な家庭の風呂場は、広くても、せいぜい大人二人が入るのが精一杯である。そして、自分で動くことができない者を、入浴させるには、どんなに力がある人でも一人では難しい介助である。病院でさえ、入院している人を入浴させるときには、寝たままの病人を、ストレッチャーで移動させて、特別な部屋で数人の看護師たちがつきっきりで体を洗う。その作業ができる機械浴の整備を整えた家庭など皆無である。
産湯を使ったその時から、日本人にとって、入浴は生活の一部であり、お風呂に毎日浸かるのは一般的な生活だ。そんな日本の風土だからこそ、木村達が始めた訪問入浴サービスは、本来は、誰にとっても必要なサービスであった。にもかかわらず、当時はだれもが利用できるサービスではなかったのだ。
1回の訪問入浴サービスの料金は、人件費に加え、交通費に車両台、水道代や湯を沸かす燃料代などを入れて、概ね1万5千円から2万円である。
このような高額なものでは、利用できる人間は限られている。毎日、いや週に1度ですら、風呂に入るなど夢のまた夢である。しかし、何年かぶりでも、お湯に浸かることができた訪問入浴サービスの利用者は、誰もが、木村や佐藤、そしてスタッフたちをおがまんばかりに感謝してくれる。汚れを洗い流すことにではない。暖まり、癒され、元気になることに、だ。
「だから、みんなが気軽に利用できる仕組みを作らなければあかんのや。」
佐藤は自分の生活は二の次にして、福祉の世界に変革を起こそうとしている。その家族たちも、夫を、息子を、父親を誇りに思い多大な援助を惜しまないでいる。
―だから自分は佐藤をバックアップし、彼とその家族の生活を必ず守り抜く。それが俺という人間の使命であり、価値なのだ。
木村たちは、自分たちの事業が軌道に乗り継続されることこそ、世の中の高齢者や障害者福祉の大きな財産になることを確信していたといって良い。
そして、彼らが次に起こした行動は、自治体への提案であった。
つづく