真っ白なホワイトボード VOL.16
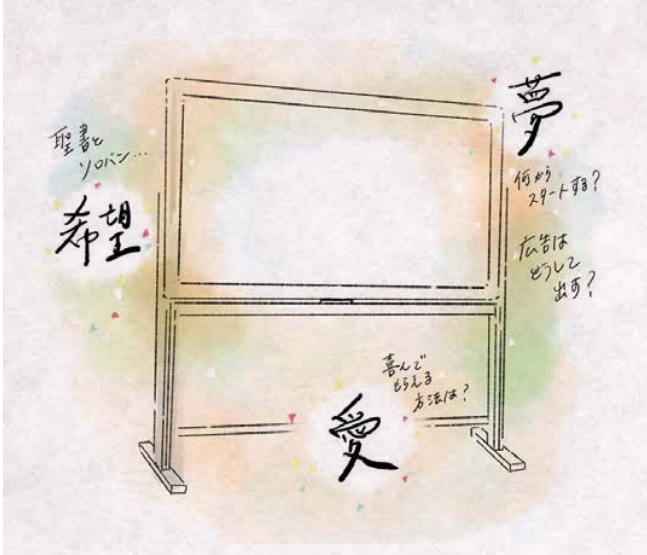
~福祉をサービス業へ、世界への挑戦物語~
第4章「革命」
その4「脱皮」
「本当によくいらっしゃいました!あなたのために料理長がケーキを焼いたの。お好きなのを好きなだけとって食べてくださいね」優しい笑顔で迎えてくれた若い女性の施設長は、開口一番そう言った。
あたたかく大きなウェルカム!のもてなしに、遠い場所に来たにも関わらず、桜田恵美は、心から安堵し自宅に帰ってきたような心地がした。
入社の翌年、佐藤からの指示で、桜田はアメリカのケア施設を視察しにきたのだった。そのひとつであるシアトルの女性施設長はまだ30代という。日本ではまだ、女性の施設長さえ珍しい存在である。
彼女は、ご入居のお客様に最高の敬意をもって接し、まるで家族のように親しく話し相手になっていた。日本でよく見かける、幼稚園児に話しかけるような言葉遣いは一切ない。一人の人格者と敬いつつ的確なケアをしている。
案内してもらった施設の庭園で「この場所から見る夕焼けが最高なんですよ」と話す彼女の姿は、たくましく、清らかで美しかった。彼女もまた、一人の人格者であった。
あまりの居心地の良さに桜田は、このままここで仕事を続けたいとさえ思った。
佐藤が入社間もない桜田をアメリカのケア施設の視察旅行に向かわせたのには、理由があった。日本で初めて介護事業を民間の株式会社として立ち上げから五年経ち、有料老人ホームの運営も軌道に乗りつつある。木村と二人で漕ぎ出した手漕ぎの船は、今や乗組員も増え、エンジン搭載の大型船になりつつある。佐藤の先見性と木村の経営手腕が、より大きな海へとその船を進めようとしていた。
「介護こそ最高のケアサービス業でなくてはならない」その理念を具現化するものこそ、船を動かすもととなるものである。
「桜田ならきっと見つけてくる」佐藤には確信めいたものがあった。
桜田は佐藤に入社を決めさせた自らの言葉通り、ヘルパーとしてホームの入居者のために、常により良い工夫を考え実践に移し、ひたすら動き回っている。ホームの清掃をし、花をいけたり、毎日違うメニューを考え手作りの朝ごはんを提供したり、求めに応じて買い物や散歩に一緒にでかけたり、いつ休むのだろうと思うぐらい獅子奮迅の働きの日々である。
それはいい。しかし、それは彼女個人の動きであって、周りの人間をも巻き込むものではない。
彼女はよくやってくれる。他の人とは違う。特異なヘルパーだ。
それでは、この介護の世界は変わらない。誰もがいつでもどこででも、彼女のような行動がとれるようでなくてはならない。
それこそが佐藤と木村が、二人で目指してきた介護革命なのだ。
視察を終えて帰ってきた桜田に、佐藤は、ホーム長というステージを用意していた。
つづく