真っ白なホワイトボード VOL.6
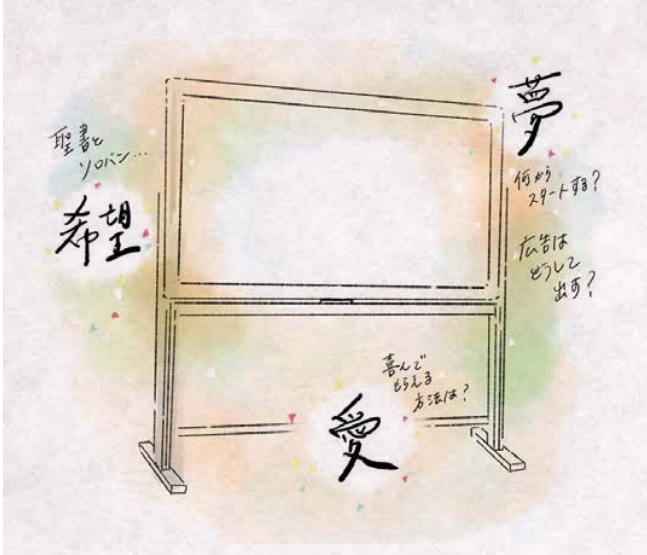
~福祉をサービス業へ、世界への挑戦物語~
第2章「介護はサービス業」
その1「木村と佐藤」
関西福祉ケアサービス株式会社の設立は1986年9月。介護保険制度の施行は、その3年半後の2000年4月のことである。その当時の訪問入浴のサービス料は1回1万5千円。会社から遠い地域によっては2万以上になることもある。利用したくても普通の家庭の財政では負担が大きすぎる額である。こんなに喜んでもらえるサービスなればこそ、必要とする人みんなに届けたい。だからなんとしても、自治体の委託事業としてこの仕事を進めたい。それが二人の一致した思いであった。
佐藤は関西の自治体を回って、訪問入浴サービス事業の必要性を説いて回った。しかし、どの自治体の役人も取り合ってくれない。訪問入浴のサービスがどういったものであるのかを知ろうともしない。31歳の若者の情熱は、行き場の無い悔しさに、打ちひしがれた。
「この仕事は絶対続けなければあかん。続けると決めたんや。そのためにできることは、何でもやろう。給料ゼロでもええ。お前と一緒にやっていく。」木村は、佐藤を励まし続けた。
佐藤の無鉄砲さは、木村もよおくわかっている。そして、その情熱は、いつも他人を喜ばせるため、困っている人をほうっておけないという止めようもない使命感から来ていることも理解していた。ならば自分は、佐藤という稀有の人間を支えることに徹していこう。木村の腹はとっくに決まっていた。
二人は社員の給料を支払うために、本業ではない副業を数多くやることになった。便利屋、露天商、宝くじ売り場、たこ焼き屋、うどん屋、ガードマン…。どんな仕事をするにしても、次々と新しいアイデアを出してくる佐藤。水を得た魚のように、それは、人を喜ばせ、楽しませ、まとを射て、本業よりも順調であった。そして、それが、木村には面白くて面白くて仕方なかった。31歳、独身の木村は、佐藤の姿から、働くことの歓びを得ていた。
「なあ、マアちゃん。」夜勤明けの警備の仕事を終えて帰りかけた時、佐藤が呼び止めた。珍しく、昔の呼び方で話しかけられて、木村は一瞬めんくらった。
「どうしたんや、シンちゃん。」木村も、友人としての呼び名で返した。
「ん、最近な、小学校時代のこと思い出してな。俺って変わってるやろ。自分はひとと違う人間で、ひとと違う生き方をしたいとずっと思ってたんや。そしてそう生きてきた。そやけど、どうしようもなく不安になることがあってな。人と違う生き方をして、野垂れ死にするようなことになるかもしれん。小学校でそんなこと考えてたんや。ふと思い出してしもた。」
黙って佐藤の話を聴いていた木村はにこりと笑って言った。
「佐藤は絶対に野垂れ死になんかせえへんわ。だって働くことが好きやん。こないに動き回って、働いてる人間は、野垂れ死にしたくてもでけへんで。」
―いや、俺がさせへん。木村は、自らに言い聞かせるようにつぶやいた。
つづく