真っ白なホワイトボード VOL.10
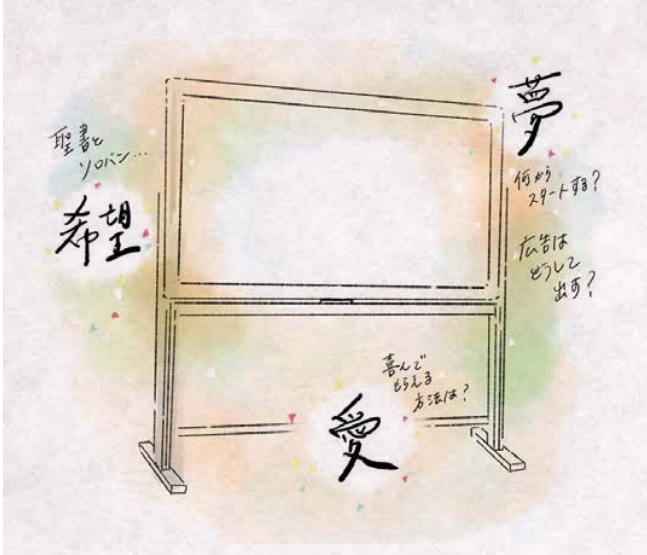
~福祉をサービス業へ、世界への挑戦物語~
第3章「裏切りから、成長へ」
その2「放浪」
残っていた社員総出で受けていた在宅介護の仕事をこなす日々が過ぎた。ホワイトボードに書かれた訪問予定宅の最後の一軒を消すと佐藤は、そのまま会社から姿を消した。
佐藤は情動の人間だ。他人への思いが強いだけに裏切られた時のショックは大きいに違いない。そう思って木村は佐藤の心が鎮まるまでそっとしておこうと思った。だが五日たっても六日たっても佐藤からの連絡はない。
佐藤と対照的に木村は理詰めでモノを考える人間だ。なぜ社員の大量辞職が起こったのか。自分たちは福祉という言葉にとらわれ過ぎていたのではないか。お客様に喜んでもらうには運営側の少々の我慢は仕方ない。そう思っていなかったか。そのシワ寄せが社員に向かっていなかったか。今一度組織としての在り方を問うてみた。会社の意義の第一は世の中の役に立つことであるが、雇用を創出し税金として社会に還元することでもある。採算を度外視して継続できる事業などない。自分たちに欠けていたのはその視点ではなかったのか。株式会社として儲ける仕組みを作らなければならないのでは…。
「なあ佐藤、どう思う」
会社の窓の外を流れていく雲に向かって木村は問いかけた。
同じ頃、漁港の岸壁に腰掛けて佐藤も空を見ていた。ふと脳裏に過るものがあった。事業をスタートさせてまもなく、訪問先に足を踏み入れた佐藤は惨状に息を飲んだ。老齢の女性が布団に寝かされていた。オムツ替えを怠っているため畳は腐って異臭が凄い。家人は玄関先に黙ってご飯を置くだけで寄り付きもしない。見かねて注意をした。
「そのために来てもらってるんや。他人の家のことに口だしするな」
あの時の無力感が再び佐藤を襲った。頭をかきむしりながら佐藤は考えた。
在宅介護には限界がある。サービス重視の介護こそ自分たちの理想とするものではなかったのか。それを実現もしないでこんなところでつまずいてどうする。
バス停目指して佐藤は走った。佐藤の目に精気が戻っていた。少年時代に泳いだ海は、あの時のように佐藤に進むべき道を教えてくれたのだ。
つづく